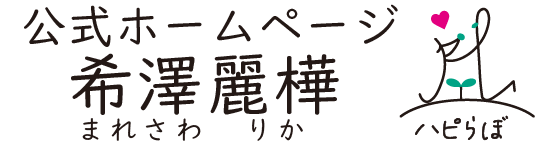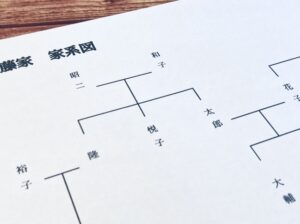あてがわれた部屋の窓いっぱいに、
根室海峡が横たわっていた。
夜明けの海を眺めながら、ふと考えた。
人は、なぜ野生と出逢いたがるのだろう。
それは憧れか、畏れか。
それとも、自分の中に眠る野生を
確かめたいのかもしれない。
けれど一度、線を踏み越えてしまえば、
その出会いは「事故」へと変わる。
ヒグマと人間の境界線は、
思っているよりも脆い。
そのことを、わたしは、
知床での数日間で深く思い知った。
突然、夫が言った。
それが、7月末の出来事。
「飛行機のマイルの期限が切れてしまう。
もったいないからどこかへ行こう」
日本のほぼ中央にある名古屋で暮らす者にとって、
飛行機で移動するのは、国内であれば
東北・北海道、九州や沖縄くらい。
それ以外の地域は新幹線の方が便利だ。
だから「空を飛ぶ」というだけで、
旅は特別な響きを帯びる。
海外に行くほどの時間は取れない。
一泊二日か、長くても二泊三日。
そんな制約のなかで
「北か、南か」の選択が委ねられ、
わたしは迷わず「知床」と答えた。
夏ならクジラやイルカ、シャチに逢える。
この時期しかないと思った。
8月最終週の平日だけ、
わたしのスケジュールが奇跡的に空いていた。
SNSには毎日のように、
悠々と泳ぐシャチや、
跳ねるイルカの姿、
立派な尾びれを誇る雄々しいクジラの写真が
投稿されていた。
「あと一ヶ月後、あの光景に逢える」
そう思うと、胸は高鳴った。
ところが、空港での搭乗待ちの間に、
その期待はくじかれた。
携帯電話の声が告げたのは
「欠航」という知らせだった。
知床の海は荒れていて、この数日間、
ホエールウォッチングの船は
一便も出ていないという。
わたしたちが予約していた便も
すでにキャンセルが決まっていた。
もう宿も飛行機も動かせない。
ならば行くしかない。
女満別空港からレンタカーを走らせ、
羅臼へと向かう。
知床峠越えのルートを選んだことを後悔した。
途中、霧に包まれた峠道では、
シカやキタキツネが姿を見せた。
「おぉ~~ 知床だ! ついに来た!!」
興奮気味の声も、
いつしか力がなくなっていった。
やがて陽は完全に落ちた。
日本一日の出が早い地は、
日本一日の入りも早い。
こんな当然の自然のサイクルにも予め気づけないはど、
都会暮らしで感覚が麻痺していると思い知った。
真っ暗闇で、濃霧の山道。
視界はゼロに近く、
フォグランプをつけても心細い。
ハンドルを切り間違えれば、
崖の下へ・・・。
きっと、誰にも気づかれないに違いない。
むしろヒグマに遭遇するより
スリリングな夜のドライブだった。
宿に着くと、スタッフさんが、
ホエールウォッチングの代替案として、
「半島の東端まで行ってみるといい」と教えてくれた。
翌朝、教えられた道を進むと、看板が出ていた。
「この先、キケン! 道なし!」の文字。
知床半島、車で進める最先端だった。
行き止まりの海。
灰色の空と、荒れる波。
打ち寄せられた昆布の匂いが潮風に混じり、
わたしは溶岩の岩に腰を下ろし思いを馳せた。
この向こうに、国後島がある。
見えているのに遠い島。
事前に資料館で、その歴史を
学んでいたこともあり、胸が痛んだ。
地元の人にとっては日常の痛みであることが、
旅人のわたしにも、ずしりと落ちてきた。
帰り道、羅臼昆布を扱う番屋に立ち寄った。
海の香りが満ちた空間で、
おばさんが笑顔で迎えてくれる。
「いいところですね」とわたしが言うと、
おばさんは「でもクマが出るよ」とあっさり答えた。
「なにもしなければ、あっちも知らんぷり。
でも立ち上がると大きいから、やっぱり怖いよね」
そして少し声を落として続けた。
「クマも人を襲えば打たれてしまう。
気の毒だけど、元は人の問題なんだよ」
クマを怖れるでもなく、美化するでもなく。
暮らしの中で実感してきた言葉は、
わたしの心に深く沁みた。
ビジターセンターでは、
ヒグマと人との距離を守るための
取り組みが紹介されていた。
路上を平然と歩くクマ。
観光客が車を並べ、まるでショーのように眺める。
レンジャーが駆けつけ、観光客を追い払い、
クラクションや大声でクマを森へ戻そうとする。
だが、クマは悠然と歩き続ける。
もはや人を怖れなくなった個体。
これが人身事故につながる前兆なのだと知った。
レンジャーは先端がゴムの威嚇弾を放ち、
犬を二頭走らせて森へと追いやる。
その地道な作業と、
ヒグマの行動監視を続ける姿を映像で見ながら、
わたしは「人の行動が、距離感を狂わせている」
という事実を実感した。
本来のクマは、人が近づけば避けていく。
だが人が「会いたい」と願い、
餌を与えたり、ゴミを残したりすることで、
その距離は崩れる。
結局、人もクマも、命を落とすこととなる。
「駆除すべきだ」と叫ぶ声もあれば、
「殺すな」と怒る声もある。
だがどちらも極端で、
自然の調和を見失った人間の論理に過ぎない。
思えば、今回の旅では一度も船が出なかった。
クジラに「逢えなかった」こと。
それ自体が、自然からの答えだったのかもしれない。
自然は、人間の都合に合わせて
姿を見せてくれるわけではないのだから。
知床の端っこの海岸に腰を下ろしたとき、
そのことを強く思った。
目の前に広がるのは、
どこまでも続く灰色の海。
厳しく冷たいその海の奥では、
魚が泳ぎ、クジラやイルカたちが確かに生きている。
すぐそばで、水鳥が潜っては浮かびを繰り返し、
小さな漁をしている。
その姿が、この海が豊かな命の源
であることを証明していた。
ここで獲れる魚は、
遠く都会の食卓にも届き、
私たちの台所を満たしている。
目の前にあるのは、海の恵み。
それをいただいて生きている。
その事実が、胸に迫ってきた。
いのちの循環。
恵みの循環。
その大きな環の中に
自分も組み込まれているのだと感じ、
自然と感謝があふれた。
知床半島。
世界遺産。
その大自然の沈黙を前にして、
わたしは人間の傲慢さと、
自然への畏敬を、ただ深く覚えた。
私たちはただ、ここに
「お邪魔させてもらっている」存在にすぎない。
「共生」とは、美しい言葉を掲げることではなく、
境界線を守ること。
距離を尊び、静かに見守ること。
そのことを、この旅は教えてくれた。
ヒグマとの境界線を学んだ旅は、
私たちが日常で守るべき「心の境界線」も教えてくれました。
これは、あなたのすぐ隣にいる
ペットとの関係にも重なります。
あなたにとって、その境界線は
どこにありますか?
少しだけ考えてみてくださいね。
過去記事も読めます